子どもの頃の私と読書
「漫画でもいいから本を読み!」
これは、中学1年生の時に母親から言われた言葉です。当時の私は、本を読むことがとにかく苦手でした。活字を追うのが億劫で、教科書すら読むのが面倒だと感じていました。もちろん、読書感想文の宿題は苦痛でしかなく、なんとかあらすじを適当にまとめて提出していたものです。
そんな私にとって、漫画は比較的読みやすい存在でしたが、それすらも積極的に読むことはありませんでした。周囲の友人が夢中になって読んでいるのを横目に、私はスポーツやゲームのほうに興味を持ち、本とはほぼ無縁の学生時代を過ごしていました。
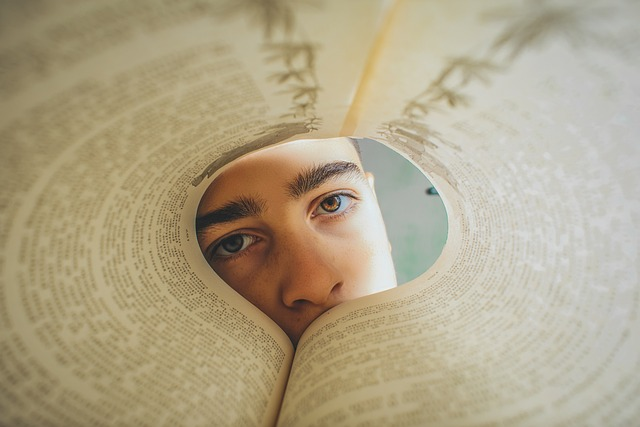
教師になってからの「学び直し」
そんな私が「読書の力」に気づいたのは、教師になってからのことです。仕事を始めて数年が経ち、子どもたちに学びの楽しさを伝える立場になったものの、どこか自分自身の学びが足りないと感じるようになりました。
そこで、30歳のときに大学院への進学を決意しました。教育についてもっと深く学びたいと思い、働きながら学ぶ道を選んだのです。
大学院では、これまでの人生で経験したことのない「本を読む」という課題が山のようにありました。専門書、論文、文献……どれも簡単には読み進められないものばかりで、最初は途方に暮れました。しかし、読まなければ授業についていけない。レポートも書けない。
そうして半ば強制的に本と向き合ううちに、少しずつではありますが「読む力」がついてきました。最初は難解に思えた文章も、繰り返し読むことで理解できるようになり、新しい知識を得る楽しさを感じるようになったのです。
読書がもたらした変化
本を読むことで、私の考え方や仕事への向き合い方が大きく変わりました。
1. 知識の蓄積が自信につながる
大学院での学びを通じて、教育理論や心理学、教育史など、幅広い知識を得ることができました。これらの知識は、実際の授業で活かせるだけでなく、児童への指導にも役立ちました。新しい知識を持つことで、自信を持って子どもたちと接することができるようになりました。
2. 思考力と視野が広がる
読書をすることで、自分の価値観にとらわれず、さまざまな考え方や価値観に触れることができるようになりました。例えば、教育に関する本だけでなく、ビジネス書や自己啓発書も読むようになり、「教師」という枠にとらわれずに考える習慣がつきました。これは、教師という狭い世界にしかいなかった自分を押し広げることにつながりました。
その結果、大学まで進学するのが当たり前!といった自分と同じような生き方がスタンダードではなく。「大学まで進学する以外にも、ちがった生き方があってもいい。その子自身が幸せなら、どのような人生を歩んでもいい。」そういった視点を持つことができるようになり、教師という仕事への向き合い方もより深くなりました。
3. 生活が豊かになる
読書は、単に知識を得るためだけのものではありません。小説やエッセイを読むことで、感受性が豊かになり、心に余裕が生まれることも実感しました。仕事で疲れたとき、本を開いて違う世界に触れることで、リフレッシュすることができるのです。
読書が苦手だった私が実践した「読書術」
読書が苦手だった私が、少しずつ本を楽しめるようになったのには、いくつかの工夫があります。それを紹介したいと思います。
1. 気になった本は、どんどん買っておく
本を読む習慣をつけるためには、まず「本が身近にある環境を作る」ことが大切です。私は、YouTubeで紹介されていて気になった本や書店で気になる本を見つけたら、迷わず購入していきました。そして、買った本をリビングや書斎、枕元といたるところに置いていました。ふとした瞬間に手を伸ばす距離に本があるような環境を作りました。そうしておくことで、「読みたい!」という気持ちが自然と生まれたときに、読むという行動にうつすことができました。
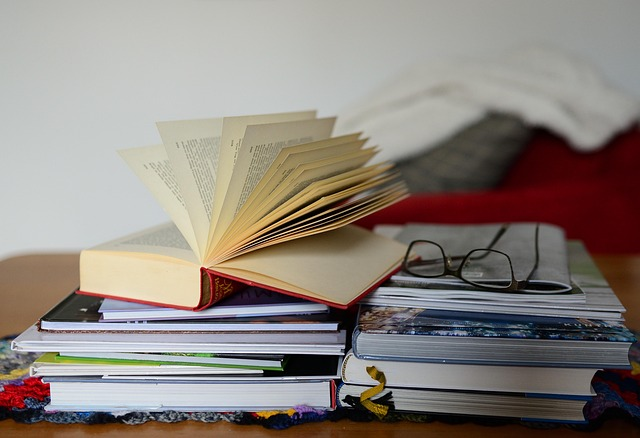
2. 今、興味のある本を読む
ネットで買って手元に届いたときには、ちがうことに興味を示していることもあります。その時に、「せっかく買ったから、もったいないから読まな」と義務的な気持ちで読むと、全く内容が入ってきません。読書がどんどん嫌いになっていきます。
そこで、私が心がけたことは、自分が今興味を持っている分野の本を選ぶことです。その日、上司とうまくいかず悩んだ日は、コミュニケーションに関する本を読んだり、貯金が貯まってきたのでうまく運用したいなと思った時は、投資の本を読んだりしました。その瞬間に興味のあること内容なら、自然と読み進めることができました。
3. 買った本だからと言って、全て読む必要はない
「お金を出して買ったから、最後まで読まなければならない」という考えを手放しましょう。途中で「この本は自分には合わないな」と感じたら、無理に最後まで読む必要はありません。私も実際、買ったけれど一度も開かない本は、いくつもあります。
なぜこの考えをするのかというと、本を読む時間も貴重な資源だからです。例えば、その本を読むのに3時間かかるとします。自分の時給を1,500円と考えると、その3時間は4,500円に相当します。もしその本が4,500円以上の価値を生み出すなら、読むべきですが、それ以下の価値しか感じられないなら、無理に時間を費やすのはもったいないと言えます。
何より本は、義務ではなく楽しみや学びのためのものです。自分にとって価値のある本を選び、読んでくださいね。
4. 本を読む目的を決め、それを解決できそうな章から読む
本をたくさん読めない。本を読む時間がとれない。そもそも本は読めない。そんな人は、最初から順番に読む必要はありません。特にビジネス書や自己啓発書などの実用書は、目次を確認し、自分の目的に合った章から読むのがおすすめです。なぜこのような本の読み方を勧めるかというと、2つ理由があります。
1つ目は、多くの本の中で著者が本当に伝えたい核心部分は、全体の約2割程度と言われています。そのため、すべてのページをじっくり読まなくても筆者が伝えたいことをつかむことはできるからです。
2つ目は、「この知識を得たい」「この問題を解決したい」といった明確な目的を持って読むことで、本の内容がより頭に入りやすいという効果があるからです。私も大学院時代、たくさんの本を読むことが大事と教えられ、多くの本を読もうとしました。しかし、気づくと「本を読むこと」が目的になってしまい、肝心の内容が入っていないこともしばしばありました。自分は、この本を読むことで何を解決したいのか、目的をはっきりさせてから読むことが大事です。
まとめると、本を読む前に、この本を読むことで何を解決したいのかをまず決めましょう。それから目次をめくり、自分の課題を解決できそうな章から読んでみてください。私なんかは、他の章は読んだことはないけど、ある章は何回も読み直している本だってあります。本は前から順に読むというルールはありません。本の読み方はもっと自由です。そういう気持ちで本を読みだすことで、気持ちも楽になりませんか。すべてを読むことにこだわらず、自分にとって価値のある読書にしょう。
まとめ
子どもの頃、本を読むのが苦手だった私が、大人になって読書の力を実感するようになりました。大学院での学びをきっかけに、読書が習慣となり、新しい知識を得る楽しさや、思考力の向上、視野の拡大を実感しました。
読書は、知識を得るだけでなく、人生を豊かにする大切な習慣です。もし「本を読むのが苦手」と感じているなら、まずは興味のあるジャンルの本から始めてみてください。短時間でも継続することで、きっと読書が楽しくなってくるはずです。
本は、私たちの人生をより良いものにしてくれる最高の相棒です。あなたも、自分に合った読書スタイルを見つけてみませんか?


コメント